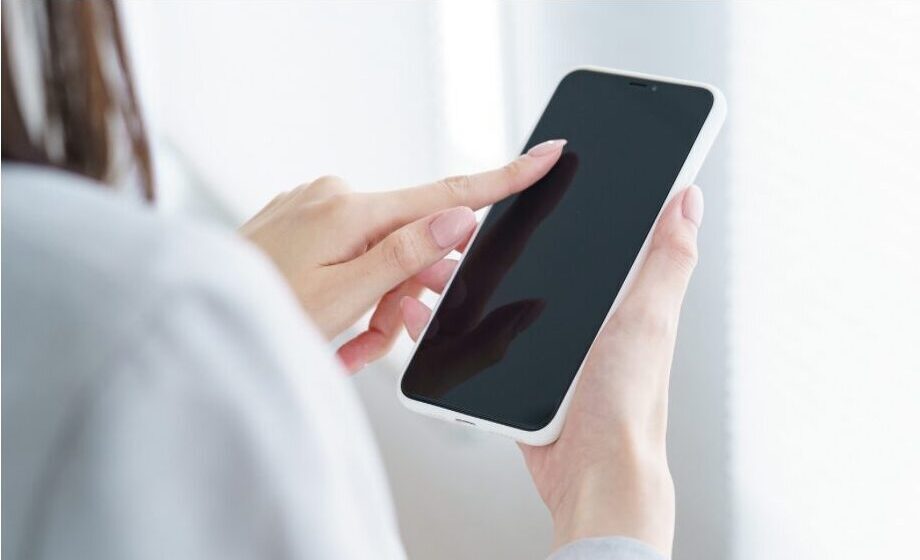ホクロとは
ホクロ(melanocytic nevus / 色素性母斑)は、メラニンを作る細胞(メラノサイト/母斑細胞)が増えてできる良性の皮膚腫瘍です。先天性のものも、思春期〜成人以降に増える後天性のものもあります。多くは無害で経過観察が可能ですが、ごく一部は悪性黒色腫(メラノーマ)と紛らわしいため、自己判断せず専門家のチェックが推奨されます。
代表的なタイプ(臨床像の呼び方)
- ウンナ(Unna)母斑
やわらかく乳頭状(ぶつぶつ)に盛り上がるタイプ。頸・腋・鼠径や体幹に多く見られます。脂漏性角化症(いわゆる「老人いぼ」)や軟性線維腫に似ることがあります。 - ミーシャー(Miescher)母斑
顔面や頭髪部にできやすい半球状ドーム型。ときに毛が生え、加齢とともに肌色に近づくこともあります。 - スピッツ(Spitz/Reed)母斑
小児〜若年に多く、赤〜黒色で急に大きくなることがあり、メラノーマと非常に紛らわしいため変化する病変は切除生検が推奨されます(“starburst”パターン)。 - クラーク(Clark)母斑=異型母斑(dysplastic nevus)
いわゆる「境界が不明瞭・色むら・やや大きい(>5mm)」などを示す“ふつうと違う見た目”のホクロ。中央がやや盛り上がり周辺が淡く広がる“目玉焼き(fried-egg)”の外観をとることがあります。メラノーマと混同されやすいため、経時的な観察や生検の対象になります。
※上の名称は「形・できやすい部位・ダーモスコピー像」に基づく臨床的な呼び分けです。診断確定は病理(顕微鏡)で行います。
自宅でできるセルフチェック(ABCDE/アグリーダックリング)
- Asymmetry(左右非対称)
- Border(縁がギザギザ/不整)
- Color(複数色)
- Diameter(直径6mm超)
- Evolving(大きさ/色/形の変化、出血/かさぶたの反復 など)
当てはまる項目がある、「他のホクロと見た目が違う(Ugly Duckling)」、新しく出て短期間で変化しているなど、このような場合は早めに受診してください。
よく似ているが別物の病変(鑑別)
- 悪性黒色腫(メラノーマ):足裏や爪などにも発生。進行が早く命に関わる皮膚がん。ABCDEや変化のある色素斑は要受診です。
- 脂漏性角化症(老人性いぼ):茶〜黒色で“貼り付いたように見える”盛り上がりで良性です。
- 軟性線維腫(スキンタッグ):首・脇など摩擦部の肌色のやわらかい突起で、良性のもです。
- 皮膚線維種:四肢にできる硬い小結節。虫刺され後に出ることあり。
- 基底細胞がん(BCC):顔面中心(鼻・まぶたなど)に多い皮膚がん。テカリのある結節、表面の血管、治りにくいびらん/出血を繰り返すのが典型です。早期に切除で予後良好なものです。
「いぼ(疣贅)」とは
いわゆる「いぼ」の多くは、ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)が小さな傷から皮膚に感染して生じるウイルス性疣贅です。自然消退も多い一方、数や痛み・場所によっては治療を行います。
主なタイプと部位の傾向
- 尋常性疣贅(いわゆる“普通のいぼ”):手指や膝、爪周り。カリフラワー状でざらざら。
- 足底疣贅(うおのめ状/ミルメシア):足裏に押すと痛い病変。皮膚のシワが途切れ、削ると黒点(毛細血管)が見えます。HPV1(ミルメシア)やHPV2(モザイク状)などが関与します。
- 扁平疣贅(若年性いぼ):顔や手背、スネに平らで小さい多発丘疹。ウイルスの型としてはHPV3/10が多いです。
- 糸状疣贅:顔面に細い突起状のもの。
うつりやすさとセルフケア
- 引っ掻き・剃毛で自己接種(広がる)しやすい。むやみにいじらないこと。
- プールや家族内で直接接触でうつる可能性。タオル共用を避けるなど基本的な対策が有効。
診断のポイント
- 角質を薄く削ると点状の黒点(毛細血管)→出血)が見えるのはいぼの手がかりとなります。
- 足裏:横から圧すと痛いのはいぼ、真上から圧すと痛いのはうおのめ/胼胝のことが多いです。
- 迷うときはダーモスコピーや病理検査で確定します。
施術内容の詳細(ホクロ・いぼ・小腫瘍)
- 深部の母斑細胞まで除去しやすく再発が少ない
- 病理検査で確定診断が可能(悪性所見の見落とし予防)
- 縫合が必要/傷跡が体質・部位により目立つことがあります
- 胸・肩・耳・首などは肥厚性瘢痕・ケロイドに配慮(テーピング等の予防を併用)
※診断未確定の色素斑は、まず切除して病理検査で安全確認するのが原則です。
- 止血しやすく、ダウンタイム中の出血を抑制
- 薄い蒸散で段階的に削れるため、部位に応じたコントロールが可能
- 小型のホクロ、脂漏性角化症、軽度の凹凸・瘢痕などに応用
- 深部の母斑細胞が残ると再発することがあります
- 凹み・色素沈着の可能性/ケロイド好発部位・体質では慎重に
- 診断未確定の色素斑は原則として切除+病理検査を推奨
術後14日目までは軟膏+テープ保護を継続。以降もしばらく摩擦・乾燥・紫外線にご注意ください。
- 傷が小さく、部位によっては目立ちにくい
- 鼻など高緊張部位での変形リスクを抑えやすい
- 深くくり抜くと凹み・肥厚性瘢痕の可能性
- 大きい病変では治癒が長引く/変形の懸念
軟膏+テープは14日目まで。以降は摩擦・乾燥・紫外線を避け、色味の経過をみます。
- 大きい病変や関節・指などでも確実な閉鎖が可能
- 機能と整容の両立を図りやすい
- 周囲皮膚との色調差/生着不良時の目立つ瘢痕の可能性
- 再手術が必要となる場合があります
術後はテーピングやシリコンなどの瘢痕ケアを計画的に行い、3〜12か月の経過観察を推奨します。

 無料カウンセリング予約
無料カウンセリング予約